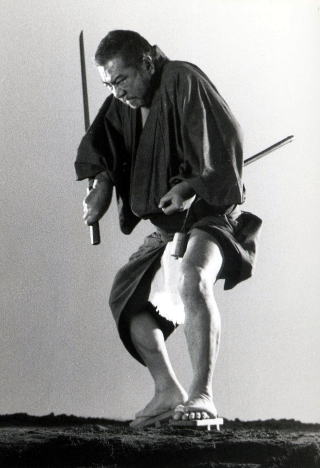友常勉(東京外国語大学教員)
スライドを見ながらロスのスキッド・ロウを語る
友常といいます。僕に要求されているのは今観ていただいた「山谷-やられたらやりかえせ」の現代的な意味を確認する、あるいは他の言葉に置き換えるということだろうと思います。その時に参照するのがロスアンジェルスのスキッド・ロウという、アメリカで有数のスラム地域で、そしてその現状を報告しながらこの映画との関係をできるかぎり語ってみるということだろうと思います。
ロスアンジェルスですが、グーグルマップのマークが付いている所が大体ダウンタウンディストリクト、まあ中心地ですね。ロスに観光に行き、最初に空港から入るとしたら、たぶんダウンタウンディストリクトのリトルトーキョーあたりに行くのではないかと思います。そこを少し拡大しますと、大体こういう感じになります。これがダウンタウンですね。お土産品なんかを買ったりするのがたぶんこのあたり。いわゆるスキッド・ロウはこのあたりに位置しています。山谷よりは大きいかもしれません。アラメダ・ストリート、サウスアラメダ・ストリートとイーストセブン・ストリート、それからイーストサード・ストリート、あとサウスマルティニ・ストリート。4つくらいの大きな道路に囲まれた地域ですね。ここがロスのスキッド・ロウというスラムです。寄せ場ではなく、スラムです。
寄せ場とスラムは違います。労働者がストリート・レイバーマーケット、道路で自分の労働力を売るのが寄せ場ですね。スラムというのは貧困者やホームレス、野宿者がそこに集住していく場所です。もともとは寄せ場に近い性格を持っていたんですけれども、やがてスキッド・ロウはスラムになっていきました。ちなみにスキッド・ロウに隣接したダウンタウン、周辺はみんな観光地でもあります。コリアンタウンとかチャイナタウンっていうのは観光地というよりは在米コリアンやチャイニーズの集住地域、まあメキシカンの集住地域とも重なっていますが、そういう地域なんです。商業地区でもあると同時に居住地区でもあります。日本人がリトルトーキョーに遊びに行ったりすると、その隣にスキッド・ロウがあります。でも、タクシーで走っていったりすると、そこには止まりません。危険な所だからということで通り過ぎることが多いと思います。地元の大学生の話を聞いたことがありますが、スキッド・ロウがどこにあるか知らなかった。山谷がどこにあるか台東区の人達が知らないのと一緒で、見ようと思わなければ見えないものですね。
あとで説明しますが、ロスアンジェルスにはツインタワーと言われている医療警察複合施設があります。これがそのツインタワーと言われているものです。ツインになっていて、手前にあるのが男性刑務所と医療刑務所が一緒になっているもの。そして奥の方にもう一つ刑務所施設があります。世界最大の刑務所と言っていいと思います。これとスキッド・ロウは深い関係があります。スキッド・ロウの北の方にはファイナンシャル・ディストリクトといって産業、ビジネスの中心街が見えます。それがどんどんスキッド・ロウの方に迫ってきています。ここら辺が産業的に開発が進んでいる所ですね。スキッド・ロウがこのあたりにあるとしたら、こちら側は少し古いビジネス街で、商店街というか、ニューヨークの五番街みたいな所です。割とコジャレたレストランとかオフィスが並んでいます。こちら側から、段差があって、エンジェルスフライト鉄道というケーブルカーがあり、それで上の地区に登っていきます。そこにはファイナンシャル・ディストリクトが上にあって、ディズニーのコンサートホールがあります。そういう文化施設のある地区がスキッド・ロウを包囲しているというのがロスアンジェルスの今の再開発の現状です。
警官やガードマンから常にハラスメントをうけているホームレス
これは僕が撮った写真と、スキッド・ロウに関わるいろんなジャーナルやニュースペーパーから取った写真です。これはミッションと呼ばれているシェルターの中の様子ですね。寝泊りすることができるので、スキッド・ロウの住人達、ホームレスの人達はこのようなミッションの中のベッドで夜を過ごすわけです。これは街の中の様子です。10年くらいここで撮影をしている写真家がいて、その写真集から取ったものです。いろんなハラスメントが警官によってされているので、その様子ですね。なかなかカメラは向けられないんですが、普通に街を歩いてればこれはしょっちゅうあることです。昼間横になってはいけないんです。朝6時から夜9時まで、路上で横になっていてはいけない。その時間に路上に寝てると逮捕されるか、あるいは警官にハラスメントされます。
壁画もたくさんあります。スキッド・ロウの住人達はこういうふうに買物かごを持っています。それに自分の荷物を預けています。ここにショッピングカート・フォー・ザ・ホームレスと書いてありまして、この買物かご、カートに窃盗、盗まれた物でないことを証明する札が付いています。これが付いてないと窃盗だとみなされるので、みんなこれを付けています。
ちょっと見えづらいですが、街の様子です。あとでこれも説明しますが、様々な支援組織があって、そこで働いてる活動家の一人です。彼に案内してもらいました。スキッド・ロウの中の彼のアパートの中に入れてもらったことがあります。小綺麗なアパートなのですが、スキッド・ロウの住民だということで安い家賃で入っているはずです。彼はニューヨークで弁護士をしていたんですが、アルコール中毒の患者になって、それでロスアンジェルスまで流れてきてスキッド・ロウの住人になった。現在はLA CANという支援組織の活動家です。
次に医療センターです。スキッド・ロウの住人だということがケア・ワーカーによって証明されれば無料で医療が受けられます。山谷の労働者、先程の映画の中でも歯がない労働者がいましたが、歯がないとソーシャル・ワーカーが口添えすれば歯の治療をしてもらえます。ですから、入れ歯をちゃんとしています。
これはミッションと呼ばれているキリスト教のシェルターの一つです。その前に、赤いポロシャツを着た男性が立っていますが、これが地元の商店街の人たちが雇っている私設のガードマンです。このガードマンが路上で寝ている者や、商店の前にいるホームレスを蹴散らすというようなハラスメントをしょっちゅうしています。ガードマンは催涙スプレーと警棒を常時携帯しています。まあこんな感じです。スキッド・ロウのホームレスの人達が路上で寝ているところをそのまま撮影するわけにもいかないので、こんなふうな風景になってますが、両側にはずらっとこうカートなりなんなりが並んでいて、左端にも見えますが、みんなそういうふうにして暮らしてます。奥の方にたぶんロス最大の警察署が見えるんですが、スキッド・ロウの中に警察署があります。山谷のマンモス交番や釜ヶ崎の西成警察署と一緒ですね。寄せ場の中に警察署がある。
スキッド・ロウの支援組織、支援団体の中にはアートや音楽を通して社会復帰をするための施設があります。これがそのLAMPコミュニティー・センターの様子です。セラピーを受けたり、居住の保証を受けたり、あるいは技術訓練、職業訓練をしたりしています。自己表現のための絵を描いたり音楽をしたりということもこの中でおこなわれています。中は結構広いんです。とても優秀なスタッフがいます。
この写真は竪川の様子、江東区の竪川の様子ですね。ちょっと写真が混じってました。スキッド・ロウから転じて竪川を見ると、なんとなく風景が似ていますから、それでつい一緒にしてしまいました。きれいにジェントリファイされた居住空間がホームレスの人たちが住んでいる空間を圧迫していくという構図は、スキッド・ロウに似てないこともない。用意している映像はこれだけなんです。あとは具体的な話をしたいと思います。ちなみにスキッド・ロウの中では様々なボランティア活動や音楽活動がおこなわれています。ヒップホップのグループのエックスクランとか、いくつかのグループがおこなっているスキッド・ロウのミュージックコンサートをユーチューブで見られます。
スラムとしてのスキッド・ロウの成立
では用意したレジュメに沿って話をしていきたいと思います。スキッド・ロウというのは今、見ていただいたようにロスアンジェルスのダウンタウンに位置しています。およそ人口1万2000人と言われています。ホームレスの数は、ロスアンジェルスは全米で最多です。そしてスキッド・ロウはロス最大のホームレス集住地と言われています。住民の貧困率は最も高く、黒人、ラティーノが中心ですね。多くはアルコール中毒とドラッグ中毒をかかえています。1970年代には住民の67パーセントが白人で黒人は21パーセントだったんですが、現在は逆転しています。
先程、ファイナンシャル・ディストリクトが押し寄せてきていると言いましたが、90年代からジェントリフィケーションと言われる、つまり貧困層、労働者階級を追い出して中・上流階級のための様々な居住施設を建設し、それに合わせた街づくりをするということが進んでいます。ジェントリフィケーションというのは同時に金融資本が押し寄せるということでもあります。中・上流階級層がマンションや様々な施設を利用するようになれば、それに合わせて保険にも入りますし、あるいは子どもを学校に入れたりもします。そういうことをして様々な資本が土地や空間を支配していくことになります。同時に、そういう階層はセキュリティー空間を拡大していきます。そして、そのセキュリティー空間は黒人や貧困層、ホームレスを犯罪者であるとみなしていきます。あるいは犯罪者視を強めていきます。これを「モラル・パニックを煽る」と言いますが、近隣住民のモラル・パニックを煽っています。
あの2007年から2008年のいわゆるサブプライムローン――低所得者層が一戸建を買えるという夢のような金融マジックがあって、それは非白人層からたくさんのお金を収奪しました。そういうことを通して、スキッド・ロウの貧困率が一気に上がって現在にいたっています。今のスキッド・ロウの近くには鉄道はないんですけれども、もともとは1870年代から鉄道が敷設され、駅もできまして、そのまわりに小さなホテルが集中してできました。それで、1930年代までに単身男性の移民労働者が集まって来たんですね。鉄道があってホテルがあって、そこに人が集まる。それに合わせてミッションと呼ばれる簡易宿泊施設がまわりにでき、さらに人が集まってきます。特に30年代の大恐慌の時代に家族を捨ててアル中になったホームレスが集まるようになりました。これが一つの契機。
それから第二次大戦とベトナム戦争です。地方からやって来た兵士や青年が一時的にスキッド・ロウのあたりに滞在します。その滞在場所になったことが契機で、帰還した兵士たちがドラッグ中毒やアルコール中毒、あるいは精神を病んだりして、結局地元、田舎に帰らないでそこにとどまるんですね。そういうことが続きます。ベトナム戦争以後というのはアルコール中毒の白人層が多かったんですが、それが80年代にはドラッグ中毒の黒人層が中心になっていきます。
現在1万2000人の住民に対してロスアンジェルス市は6500人分の単身者用の部屋を用意してます。それから2000のベッド数をシェルターとして保証しています。しかしそれだと足りないわけですね。ロスのホームレス・サービス局とかロス市警によると2000人から4500人、あるいは5000人のホームレスが路上で暮らしていると言われています。70年代から医療ケアや住居保証を進めるようになってたんですが、ボランティア活動、あるいは基金を集めるということを通してロスの様々な支援組織がつくられています。一つがロス・コニュニティー・アクション・ネッットワーク、LA CANと言われているもの、それからLAMPアートプロジェクトというものがあります。それらは住居、人権、医療ケア、社会復帰プログラムを用意しています。さらに先程見てもらったようなミッドナイト・ミッションと言われるキリスト教系の簡易宿泊施設があるわけです。で、その簡易宿泊施設に行けば、ボランティアで集められた服もありますし食べ物もあります。歯磨きだって何だってあるのですね。暮らしていこうと思えばミッションの中で暮らしていけるのです。ただ、お金は貯まりませんからスキッド・ロウから出て行くことは不可能だろうと思います。それに、無料で医療が受けられるといっても、実際そこで住むというのは大変な困難と差別を強いられることになります。
産獄複合体による刑務所収監人口の激増
アメリカのスキッド・ロウについて語るということは、アメリカで突出している産獄複合体について語ることだろうと思います。プリズン・インダストリアル・コンプレックスと言います。1980年代以降の社会というのは、日本も含めて全世界でそうだと思いますが、貧困は犯罪としてみなされます。ということは貧困者、経済的困窮者というのは監視の対象です。それが可能な社会や国家ができ上がっています。刑罰国家、監獄社会ができ上がっているのですね。そうして、そういう刑罰、監獄社会をビジネスにするというのが次の段階です。このビジネス化がずっと進んでいるのがアメリカの産獄複合体だと考えてください。スキッド・ロウの中で住民たちは日常的に警官と私設ガードマンによってハラスメントされています。簡単な罪で逮捕される。さきほども言いましたように、朝の6時から夜の9時まで路上で寝ていてはだめなのです。路上で寝ていたら、それで逮捕されますから。それで、軽微な罪で逮捕され、刑務所とシャバを普通に行き来しているんですね。すると、当然ながらブラックリスト化されます。一度逮捕されるとメンタル・チェックもされますので、それによってアルコール中毒やドラッグ中毒患者としてブラックリスト化されます。市民的権利をそれによって剝奪されます。
アメリカ社会の産獄複合体、監獄社会化についてはアンジェラ・デイヴィスの本がよく知られているので、そこからデータだけを拾っておきますと、アメリカは異常に刑務所収監人口を増やした国です。1970年から2006年の間で8倍、230万人に刑務所収監人口が達しています。さらに執行猶予および保護観察下にある者は合計720万人、犯罪経歴を根拠にして参政権を剝奪されている者は500万人に達しています。アメリカ刑務所の収監人口比率は2006年で10万人あたり750人。ちなみにロシアで600人、日本は50人というデータがあります。
収監人口が増えた一番の理由は麻薬犯罪が厳罰化されたからです。一方で、殺人犯罪件数は1990年代からずっと減少しています。日本でもそうですね。ずっと減少しています。あくまで収監人口の激増の主要な理由は麻薬犯罪で、同時に刑期が長期化していきます。長期化するとどうなるか。警察、裁判、刑務所関連予算を増やすことになります。これがビジネスにつながります。監獄ビジネスが民営化されて、民営監獄が増えているのです。過疎地があるとしたら、その過疎地を再開発するために監獄を誘致する。その中で低賃金労働がおこなわれています。さらに犯罪報道をテレビの三大ネットワークが煽るということを通して、警察、裁判、刑務所関連予算を増やす世論が形成されていきました。これを産獄複合体と言います。こういう複合体はどの国でもいつでもあるじゃないかと思われるかもしれませんが、福祉と警察、それから裁判と監獄というような様々な利益体、形態が簡単に結びついて、安易に結合したり分離したりするというのは今までになかったことでした。それができるようになっているという意味で複合体と呼びます。
アメリカのこのプリズン・インダストリアル・コンプレックスの特徴は、麻薬中毒患者を収監することを通して精神病棟の経営と監獄経営を一体化させることに特徴があります。先程あのツインタワーを見てもらいましたが、それが一つの典型です。このツインタワー自体は1500万㎡の面積で世界最大の刑務所です。男性中央刑務所、拘置所、医療施設、それから矯正施設が二つあって、これがタワー1、タワー2と言われています。ここからツインタワーと呼ばれています。全体収監人口は9500人に達しています。ちなみに日本の最大の刑務所は府中刑務所で、4500人くらいだと思います。その倍ですね。収容者は精神病の治療のために薬物を投与されます。薬物投与だから製薬ビジネスと結びついています。また刑務所の中では日常的に暴力と人種差別にさらされています。こういう報道は様々なメディアの中で伝えられています。
産獄複合体と麻薬ビジネスのシステム
配布した資料の中に、僕がインタビューをした日本人の話の一部を掲載しておきました。どのようにスキッド・ロウの住民になるかがわかる一例です。彼の名前をJとしておきますが、80年代に観光ビザでアメリカに入国。日本レストランで働いていたけれど、86年移民法の改正でレストランを解雇されたあと、89年からスキッド・ロウで暮らすようになった。仕事を失った大晦日に近いある日の夜にブラブラしてたら焚火にあたっていた黒人のホームレスに誘われて、日本人だからJなのかもしれませんが、Jという名前でそこで暮らしてるんですね。彼はビジネスとしてスキッド・ロウの中でわりと成功しているのです。
彼の話によると、住民達がどういう生活をしているのかがわかります。現在は月221ドルの州政府から出る生活保護、それからチラシ配りの日払いの仕事、それで月600から700ドルくらいになります。スキッド・ロウの住民は地区内のアパートメントホテルを格安で借りられます。ホテル代が普通は月600ドルはしますが、それが62ドルの家賃ですみます。残りは州政府が負担します。先程言いましたように、ミッションに行くと新しい服や靴、食事、それにシャワーがあります。医療ケアも受けられるので221ドルの生活保護で暮らしていけるようにみえるかもしれませんが、実際にはそれは無理です。
日本の寄せ場はすごく高齢化しています。釜ヶ崎がそうであるように生活保護を受けて生活保護者向けの福祉アパートに入ったりしています。でもスキッド・ロウの住人は凄く若いのですね。本当に若い。少年、青年もいっぱいいます。若いけれども90パーセント麻薬中毒の患者なんですね。簡単に買えますから。そこでドラッグをどんどん売ってる。バイヤー、小売人がそこらじゅうにいるからです。Jをインタビューしていた公園はもうそこらじゅうに売り子がいて、その公衆トイレの中でみんな吸引しているのです。それで年金が支給されると、小切手が支給される時にバイヤーが全部吸い上げてしまうんですね。そういう状態の中でドラッグとアルコール中毒漬けになっているのです。221ドルの生活保護を毎月もらっていたとしても早い人で1日、長くても3日か4日くらいで全部ドラッグに消えていくんです。だから、ミッションや路上で暮らすしかない。そして、人格も破壊されていくという状態が続く。ミッションの中に入れば、それなりのケアが受けられるのですけれども、外に出たらやっぱり元の木阿弥だと、Jは言っていました。
なんでこういうことが起きているのか。アメリカの麻薬ビジネスに対しては、それなりに報道されています。麻薬との戦争はうたわれているのですが、しかし最も巨大な麻薬ビジネスを運営している本体そのものを問題にして全面的に解決しようとはしていないようにみえます。むしろ麻薬ビジネスで様々な収益がある。麻薬中毒が増えれば、プリズン・インダストリアル・コンプレックスの中で利益が上がりますから。そして、そういうプリズン・インダストリアル・コンプレックスの中での利用価値、利用される意味を世論に何度も喧伝するためにスキッド・ロウのような場所が保存されているとしか理解できない状態が続いています。麻薬に対する戦争っていうけれども、それに実質がともなってない。戦争の敵だけは残しておいて、それによって戦争の犠牲者である麻薬中毒患者になっている人たちに対してハラスメントを続けているだけです。
実際、Jをインタビューしていた公園には20台くらい監視カメラが付いてるんです。隣は警察署ですよ。そこで麻薬を売っているのに、ディーラーもいるのに逮捕しようとしない。野放しなのです。日常的にそれを駆逐するための政策をおこなっているわけではないのです。これは麻薬ビジネスのシステムそのものを保存しているのじゃないか。つまりスキッド・ロウは大きな意味での産業監獄精神医療複合体の共同利益の一部になっていると考えています。『山谷―やられたらやりかえせ』の中では宇都宮病院の映像が出てきますけれども、寄せ場の運動ははじめから寄せ場の日雇労働者と精神医療の問題を気付いていて、早い段階から告発をしていました。その点で、ビジネスとして国家規模で展開されているのがアメリカの場合だと思います。
そのようなスキッド・ロウの現状をみた時に、今どういう闘い、運動が求められているのか。それはホームレスが中心になっている運動だから、居住を求める闘いというのが重要だろうと思います。2010年にスキッド・ロウの住人でLA CANの活動家であるデボラ・バートンという人が国連の定期レビューの中で、ロスのホームレスの人権侵害についての報告をおこなっています。彼女は警察によるハラスメントや移動や収監を非難して、それが国家的におこなわれている実態を批判しています。また一方でLA CANがやってる活動の意義を強調して、アメリカ政府のホームレスに対する政策と、政府の政策が産獄複合体ビジネスの末端化していることに対して、国際的に圧力をかけてくれということを要請しています。ロスのホームレスに対しておこなわれている人権侵害は国際社会が責任を取るべきことなんだと。これは1948年に採択された国連人権宣言第25条違反になります。国連人権宣言第25条は居住の権利をうたっていますから、居住の権利というものをテコにしてスキッド・ロウの現状を批判し、国際社会による圧力が可能であるということです。さらに、スキッド・ロウの支援組織はより高度な政治的なスローガンも掲げていまして、居住権を求める闘いというのは現在進行している新しい人種主義的資本主義の――彼女はそう言いますが――政治・経済に対する挑戦だと言っています。そういう国際的な運動の中に居住を求める闘いを位置付けていて、それがスキッド・ロウの闘争の中心的なスローガンの一つだということを強調しておきたいと思います。
ジェントリフィケーション――中・上流階級が貧困層を駆逐する
居住の問題にかかわって、ジェントリフィケーションについて説明したいと思います。ジェントリフィケーションというのは、簡単に言うと、中・上流階級が貧困者、労働者を駆逐して街を浄化していく、そしてアパルトヘイト化していくということを意味しています。ジェントリフィケーションの内容に関しては、90年代から2000年代にかけて、ニール・スミスを中心にして理論的に精緻な議論がされるようになりました。ニール・スミスの主著は原口剛さんの訳で『ジェントリフィケーションと報復都市 新たなる都市のフロンティア』(ミネルヴァ書房)として出版されていますので、参照してほしいと思います。とくに地代格差論について提起している部分が参考になります。これを用いて説明してみます。
たとえば山谷でも釜ヶ崎でも、そしてスキッド・ロウでもそうですけれども、様々な社会的な開発によって、自分たちを排除し駆逐する弾圧や大きな権力がやってきます。でも、いつ開発が始まるのかの予測はできないのですね。いつ開発が始まるのか。現実的にタイムスケジュールが出せるわけではないけれど、でも東京の場合だったら東京スカイツリーができ上がって、隅田川の、墨田区の向こう側から始まってきています。一方では、2020年の東京オリンピックがプログラム化されていて、まわりから地代が上がっています。そうすると今までは資本に活用されない場所、山谷のような場所や、釜ヶ崎、そういう場所は相対的に値段が下がっていく。そうして、寄せ場との地代の格差が拡大した時に、ジェントリフィケーションという開発が始まる。そして、ジェントリー資本がやってきて都市開発が進んでいき、それが階級的で人種差別的なアパルトヘイトをつくり出すことになる。これが地代格差論にもとづく説明です。
こうした性格の開発に対抗するためには、そこに住んでいる人たちがジェントリフィケーションや中・上流階級の価値観に基づかない、そういう資本の価値や階級的な生活の価値観に基づかない権利をいかに行使し、いかに社会が守れるかということになるのだろうと思います。そういう政治プログラムをこちら側からつくらないといけないということです。
ちなみに西成の釜ヶ崎では、西成特区構想というのを橋下市長が提起し、さらに「あべのハルカス」という商業施設がつくられて都市再開発が進められています。これはジェントリフィケーションが釜ヶ崎で起きていることだろうと思います。そして山谷でもそれが迫りつつあるのではないか。で、それに対抗していくためのこちら側の、ジェントリフィケーションや開発ではない価値観に基づく運動、地域社会づくりが必要になるだろうと思います。
釜ヶ崎や山谷をはじめ、様々なところでみられる日雇労働や重層的下層労働、もちろん原発での除染労働も入るのですけれども。そういう労働の中で問われている課題に答えるために、今、関西や東京の友人たちと一緒に、従来の寄せ場の労働運動、そして様々な現場の闘争の歴史の読み直しをしています。その読み直しの中にはイタリアのアウトノミア運動とか現在の反グローバリゼーションの運動も含まれています。そういうことを通して、かつての寄せ場、現在の寄せ場を自律的な空間として再創造する、そのような活動を一緒にできればいいなと思っています。
ホームレスに対する差別的心理は連鎖的に形成される
司会 50年ほど前は産学協同というのが批判されましたが、それを飛び越えましていまや産獄複合体というとんでもない時代になってきたなあと。時間がまだちょっとありますので、なにか質問あるいは意見がある方はどうぞ。はい。
参加者A ちょっと用事があって映画は観られなくて、講演を聞くためにやって参りました。ニューヨークのジュリアーニ市長時代の、いわゆる割れ窓理論の一種の神話化、批判は出ているものの再び最近、日本のマスコミなんかでは割れ窓理論が常識みたいなことを言う人が多いんですよね。ラスベガスやニューヨークが浄化して成功した例として、今だに日本だけじゃないと思いますが、マスコミとかビジネス・スクール系とかで、取り上げられてます。それが西洋から非西洋世界にも広がりつつあるということに対して、友常さんの、我々の側の対抗論理って言うんですか、どう対抗していくかということでヒントをいただければと思います。
友常 こういうことを始めたのは最近なので、ニール・スミスのサーヴェイにならって考えるしかないのですけれども。ジェリアーニとその前の市長の時代におこなわれていた政策の中で、結局トンプキンズパークから追い出されたホームレスたちはどこに行ったかというと、JFケネディの空港からダウンタウン、マンハッタンに入るまでのドライブのあたりですよね。あのあたりに全部追いやられていった。高速道路のまわりに塀で囲まれた所にホームレスが押しやられていくわけです。そこに追いやられてしまうと、もう見えなくなってしまっているのですね。だから成功したっていうよりは見えなくなったということです。そうして見えなくさせられたということで、大きなモラル・パニックみたいなものを防いだということです。そこで議論が沈静化したわけです。でも、その後も問題は残っていて、その高速道路のまわりの中・上流階級の住民達が今度はその新しいホームレスに対する差別と敵対を強めていくわけです。それで随分、問題になっていたというのは聞いています。
白人だけじゃなくてアジア系も入るのですが、中流階級層、上流階級層のモラル・パニックがとても上手に利用されていったと思います。その時にニール・スミスが報復主義として整理した議論がすごく有効です。ホームレスに対する差別的な心理というのは連鎖的に形成されるということだったと思います。市場や開発の理論の中にそれをうまく組み込んで説明をしないといけないのだろうと思います。その点、ジュリアーニが果たしてそこまで考えたかどうかわかりませんが、非常によく機能したのじゃないか。報復主義が差別・敵対心を市民の中に連鎖的に形成させることで、ニューヨークにおいてそれは成功したというか一定の実現をみたという気はしています。
参加者A 新宿浄化作戦も……
友常 同じですよね。結局、都市計画の議論の中に集団的に形成される差別意識をどういうふうに組み込むかということになるのだろうと思うのです。それをどれくらい地代論とか地代格差論などの議論をもって説明ができるかということにかかっているのかもしれません。活動家はすでに実感的に肌でわかっていることなのですけれども。それが市場の中で、マスメディアなども通して報復主義として機能してしまっているという現状ですね。
参加者A まずいことに、我々も日本で生活する以上は日本の産業が国際的に負けてしまうのはまずいんじゃないか、例えばシンガポールとかソウルとかに対抗して東京がもっと魅力的になるには、という議論にはまってしまいがちになるわけですね。
ジェントリフィケーションを繰りかえすのが資本のプログラム
参加者B 私は芸大で木幡和枝先生の教え子でした。先日NHKの討論番組で移民というか外国人労働者の受け入れについての番組に出ました。移民を受け入れていけば、同質性の高い日本人の方向性としては排他的な行動が出てくるんじゃないか、そしてそれによって何か社会がつくり替えられてしまうんじゃないかとみんなが漠然と思っている。友常さんは移民政策において、ホームレスに対することと同じようなことが起こるというイメージはありますか。
友常 こういう議論になると、私が答える話ではないのじゃないかという気もするのですけど。89年に日系ブラジル人の受け入れを、基本的に三世までは制限なしで拡大しました。リーマン・ショックで結局、30万円を渡して追い出してしまった。期限付きですよね。日系ブラジル人にしてもそうでしたし、それ以外の移民労働者に関しても5年とか3年という在留資格。永住も可能な、日系ブラジル人と同じような処遇の移民労働者の受け入れに方針が変われば社会状況は変わると思います。それからコード化された移民労働者の受け入れ方をするのか、それとも地域社会を含めてどんな出会い方もありえるような受け入れ方を選ぶのか、この差は大きいだろうと思います。私の大学の経験で言うと、日本人と留学生がコード化された出会いしか持たなかったらば、関係性は多様にはなりません。
『Furusato2009』という映画があります。これは『サウダーヂ』という映画を撮った富田克也さんと相澤虎之助さんたちがつくった映画です。山梨県の中央市に山王団地という団地がありまして、そこの住民は6割が日系ブラジル人で、自治会長までが日系ブラジル人です。そしてみんな仕事がない。まわりの地域社会、隣接している日本人のコミュニティーとまるで没交渉なんですね。そういう意味で、日本人とはコード化されている出会い方になると思います。そのもとで、日系ブラジル人が車上荒らしをしているというキャンペーンがローカルな所でされて、居づらい雰囲気がつくられています。開発と一緒で、一挙にではないかもしれないけれど、まわりから排除がされていく条件はいつもつくられているように感じます。
参加者C 大阪のあべのハルカスをたとえて中・上流の所得層の人達がアパルトヘイト的に人を駆逐していきますよってことですが、本当にそうだと思うんです。そうしたら、その先はどういう予測がされるんでしょうか。例えば、ホームレスの人が減るのか、減らないのか。彼らは生きやすくなるのか。生きにくくだと思うんですけども、どんなふうにこの先が待ち構えているんでしょうか。
友常 日雇の労働者達とそれから新しいホームレスがゆっくり押し出されるように駆逐されていった。そして押し出された先で、もう一回ジェントリフィケーションが起きるのだろうと思う。それは無限に続くというのが資本の運動だと思います。ここでまた起きる、そして次は山谷でと。釜ヶ崎に隣接する飛田はちょっと違うかも知れませんが、飛田もきれいになりましたからね。そこの土地の値段が下がって、あるいはまわりの土地が上がって、そこを追い出した方が資本にとって利益が上がるとしたら、追い出すでしょう。だから資本の運動にとっては土地の値段を下げるために、ある意味でホームレスが必要だったりします。産獄複合体の発想はそういうことです。その土地の値段を下げていくためにマイナスの要因が常に必要になります。価格の格差が拡がって利益が上がる時に、資本は一挙に開発すればいいわけですから。これを永遠に繰り返すというのが資本のプログラムなんじゃないかと思います。
参加者D 私は大阪生野区に10年住んでいました。生野区は在日朝鮮人がたくさん住んでいる街です。西成も釜ヶ崎も結構近くて、よくそこから日雇のバイトに行ったりしてました。ロスアンジェルスの80年代に、あのロス暴動があって。エスニック・コミュニティー同士の対立という問題にすり替えていいのかわかりませんが、そういうのがあったわけですね。そういったエスニック・タウンとスキッド・ロウとの関係はどうなんですか。スキッド・ロウでの街づくりと、エスニック・コミュニティーのロス暴動以降の関係性。資本のつながりとかはどうなんでしょうか。近くなんですか、場所は。
友常 結構離れていますね。ブロックでいうと相当離れています。二駅くらい違うと思います。1992年のロス暴動の時はスキッド・ロウも戦場になっていたと聞いています。隣にメキシカンのディストリクトがあって、繊維・衣服系の、衣料系の店がたくさん並んでいるのですが、そこは随分襲撃されました。従業員はメキシカン、ラティーノなのだけれども資本、商店主はコリアンだったっていう。だからエスニック・コンフリクトだったと思うのです。それで、コリアンタウンではロス暴動のあとエスニック・コンフリクトを和らげるような取り組みが随分進んでいましたね。一緒に協同作業をしたり、青年組織が様々な取り組みをしたりして、住民同士のつながりをつくるようになっていました。そういう意味では、商業施設の中のエスニック・ハーモニー、ハーモナイゼーションを進めるっていうのが地域のスローガンになっています。つまり資本がそういう方向で、商店主達もそういう方向で動いています。
これに対して、ではスキッド・ロウはどうか。まずスキッド・ロウそのものはそういう資本が動く場所ではないです。基本的にあそこはアパートと、それからリテール・ショップがすごく多いのです。そういうリテール・ショップの資本を持っているのはコリアンが中心になるかと思います。リトルトーキョーも実はマンションはほとんどコリアン資本、韓国資本です。たぶんスキッド・ロウにも韓国資本が入っていると思いますが、その資本家達の動向はまだ分析できていません。今現在、エスニック・コンフリクトのような自分たちの利害に関わるような問題が起きているわけではないですから。むしろメンテナンスをしないでそのままにしておいて、もっと利益が上がるくらいに劣化していった時に開発を一挙にやってしまえばいいということなのじゃないかって気がします。しかしその分析はこれからの課題にしたいと思います。
司会 まだ続きがありそうな雰囲気なんですが、この場所はここでお開きにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。時間の許す方がありましたら隣に飲み物なども準備してありますので、ゆっくりとどうぞ。
(2014.8.16、プランB)